地震発生「熱移送説」ではプレートとは異なる場所が危険に
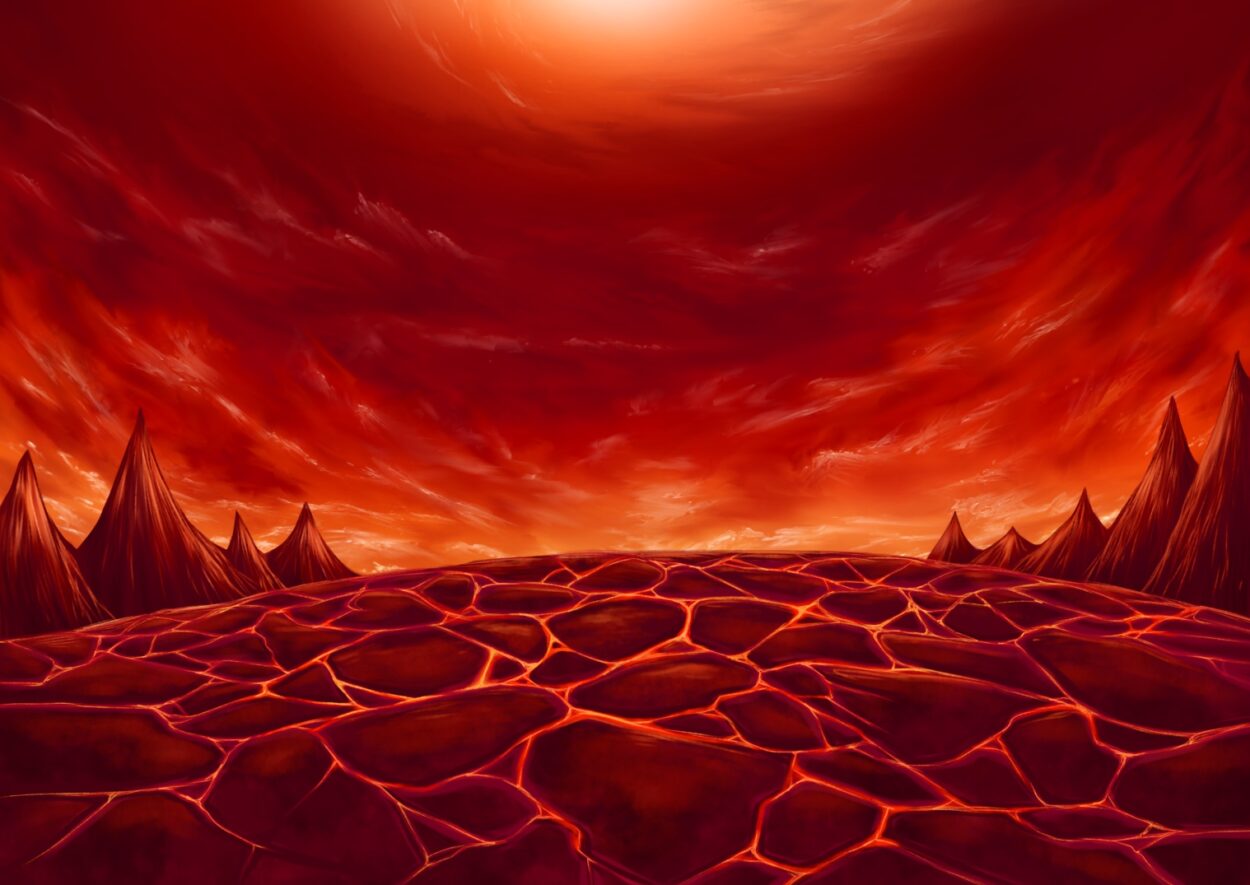
日本で地震が起きる原因として広く知られているのは、プレート同士がぶつかり合って歪みが蓄積され、それが解放されることで発生するという「プレートテクトニクス説」です。しかし、熊本地震や大阪北部地震など、プレート境界から離れた地域で発生した地震に対しては説明が難しい場合もあります。近年注目されている「熱移送説」は、地球内部の熱の移動が引き金となり、地盤の弱点で地震を誘発するという全く異なるメカニズムを提唱しています。本記事では、プレート説と熱移送説の違いや、熱移送説で危険とされる日本の地域、予測の可能性などを詳しく解説します。
現在主流の地震説 プレートの歪みが引き起こす地震とは
地震発生メカニズムとしてこれまで広く支持されてきたのは、プレートテクトニクス理論に基づく考え方です。地球の表面は数枚のプレートに分かれていて、それが相互に動くことで歪みが蓄積され、限界を超えると断層がずれて地震が起きるとされています。この説によって、海溝沿いの海底地震や活断層周辺の直下型地震の多くが説明可能です。
熱移送説とは?どのような新しい発想か
一方で、埼玉大学名誉教授の角田史雄氏が提唱する「熱移送説」は、地震の原因をプレートそのものではなく、地球内部の熱エネルギーの移動に求めています。地核から通る高温の熱はスーパープルームと呼ばれる通り道を通り、地表へ伝わります。そのルートの一つは南太平洋にあり、そこからインドネシアやフィリピンを経て日本列島に向かう二つの主要ルート、PJルート(九州方面)とMJルート(伊豆諸島・首都圏方面)に分かれて進んでいきます。
熱がたまる場所では火山が活発化し、地盤に弱点がある地点では膨張によって地震が引き起こされるとされます。熊本地震や鳥取地震、北海道胆振東部地震など、プレート理論では説明が難しいケースにも熱移送説は当てはめることが可能とされています。
熱移送説において、日本国内で危険とされる地域はどこか
熱移送説によれば、地震が起こりやすい場所は熱が到達し、かつ地盤に問題がある地点です。具体的にはMJルート沿いの伊豆諸島や伊豆半島、首都圏への北上経路が特に注目されています。例えば西之島の噴火活動から始まった熱は伊豆諸島を経由し、八丈島や千葉東方沖で地震を誘発してきました。またPJルートでは熊本地震、大阪北部地震などが発生し、その後新潟・富山地域での火山活動や地震の可能性も指摘されています。
以下の表は代表的な地域とその状態をまとめたものです。
| 地域 | 熱移送ルート | 主な活動例 |
|---|---|---|
| 伊豆諸島~首都圏 | MJルート | 西之島噴火→八丈島・千葉東方沖地震 |
| 九州~中国地方~北陸 | PJルート | 熊本地震→大阪直下型地震→新潟・能登火山活動 |
| 北海道・十勝沖 | MJ・PJ合流地点 | 胆振地震、今後の十勝沖地震の警戒地域 |
熱移送説で地震発生を予測できるのか
熱移送説によれば、熱エネルギーの速度は年間100キロメートル程度で一定であるため、火山噴火をきっかけに地震が数年後にどこで起こるかの予測が理論的に可能とされています。ただし、どの地点の地盤が脆弱かを正確に判断するのが難しく、個別の震源や時期を短期的に予測するのは難しいとの指摘もあります。早川正士氏による電離層の擾乱を用いた短期予測など別の手法と併用することで補完の可能性があります。
おわりに
従来のプレートテクトニクス説では説明しきれない地震の傾向を、新たに熱移送説は理論的に説明しようとしています。日本では伊豆半島周辺、九州から北陸にかけての熱移送ルート上の地域、さらには北海道の合流地点が特に注意が必要とされます。今後は熱推移のデータと地盤評価を組み合わせた地震リスク評価が進むことで、防災対策にも新たな視点が加わる可能性があります。


